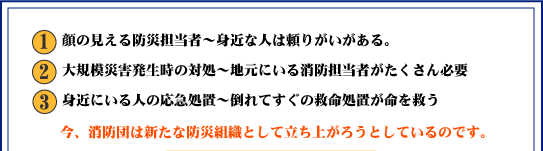|
 |
|
|
消防団は、歴史的に消防本部・消防署が出来る前から消火活動を担ってきた伝統があります。当時は火災件数も多く、被害も大きかったためその任務はきわめて重要な社会的位置をもっていましたが、常備消防の充実が図られていく中で、その主要な任務は常備消防に移り、さらに消防活動においては救急救助業務の比重が高くなり、消火活動のみを主要な任務としてきた消防団の必要性が著しく低下してきました。このことは消防団員の目的意識の低下として現われるとともに、市民の意識の中においても消防団の存在感が失われてきます。 さらに旧来の共同体意識の崩壊、相隣関係の希薄化、そして、職業構造の変化によるサラリーマン化などにより消防団活動は低迷の一途をたどってきています。名取市においても、400名の定員に対し、常に20〜30名の欠員があり、平均年齢は40代後半です。 しかし、我々は今、現代社会の特徴ともいうべき高齢化や都市型災害といった新たな課題に直面しています。まさかの事態が発生したとき、その被害を最小限に食い止めるためには、まず第一に身近にいる人同士が助け合うことが最も重要であることが認識されつつあり、常備消防が手をかけるまでの間、あるいは手がまわらない事態における身近な人の対応が人命救助、生活環境保全の成否に関わることになるのであります。常備消防の補助的役割から脱皮し、常備消防との役割分担を明確にしなければなりません。大規模災害では消防職員は手がまわらない、急病、事故では消防職員の現場到着まで空白時間がある、そのような時、まさしく地域住民による組織である消防団の新たなる任務が見えてくるのです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||